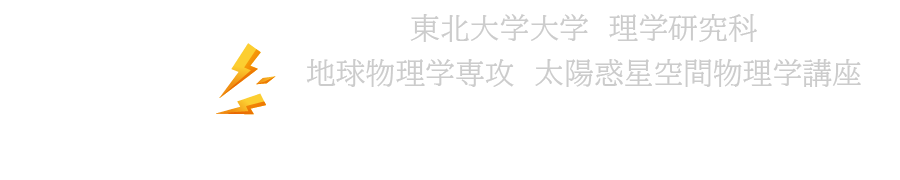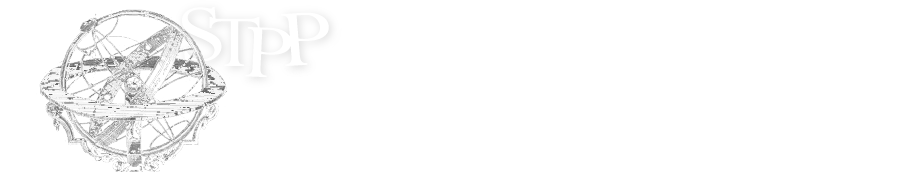令和7年度第20回STPPセミナー
令和7年度第20回STPPセミナー
2025/11/17
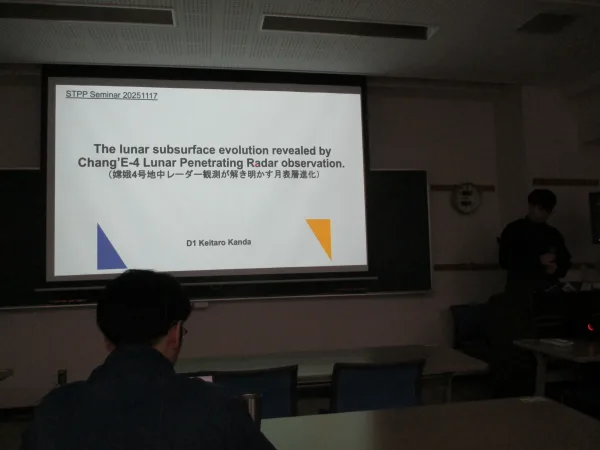
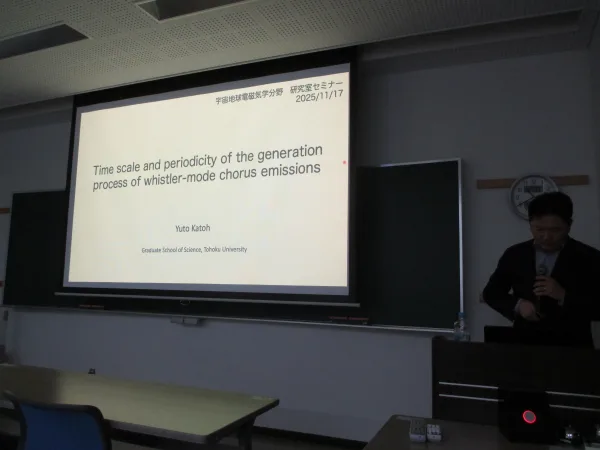
発表者:神田 恵太朗 (D1)
発表タイトル(英):The lunar subsurface evolution revealed by Chang’E-4 Lunar Penetrating Radar observation.
発表タイトル (日):嫦娥4号地中レーダー観測が解き明かす月表層進化
イントロダクションの要約:
月や惑星表面では、もともとマグマが冷えて固まったような硬い岩盤の上に、長年の隕石衝突によって岩片や砂が溜まって「レゴリス層」ができます。隕石がぶつかるたびに岩盤が削られ、最初は大きな岩塊、そこからだんだん細かい石ころや砂へと砕かれていきます。このプロセスが何十億年も続いてきた結果、表面に存在する岩の大きさと個数は、「その地表面がどれくらい長い時間、隕石衝突にさらされてきたか」を示す指標になります。
この関係を扱うのが岩石サイズ頻度分布(RSFD)です。先行研究では、若い地形では隕石衝突の影響がまだ小さいため岩の数が多く、古い地形では長期間衝突を受け続けた結果、岩の数が少なくなることが示されています。これまでのRSFD研究は、主にカメラ観測によって地表に露出している岩だけを対象にしており、地下に埋もれた岩のサイズ頻度分布は分かっていませんでした。
そこで本研究では、「地下の岩石サイズ頻度分布」を明らかにすることを目的とし、その手段として地中レーダー観測(GPR)に着目しています。地中レーダーは電波を使って地下構造を探る手法で、地球だけでなく、月・惑星探査でも広く使われています。中国の嫦娥ミッション(ローバー/着陸機搭載レーダー)や、日本とインドの共同月探査ミッションLUPEX(ローバー搭載レーダーを計画)などがその例です。発表者は特に、嫦娥ミッションのローバーに搭載された地中レーダーデータを用いて研究を進めています。
今回の発表では、これまで進めてきた地中レーダーを用いた地下岩石分布の解析をさらに発展させ、探査領域内に存在すると報告されている複数の異なる地下構造のあいだで、岩石サイズ頻度分布を比較します。これにより、同じ地域の中で異なる地下構造がどのような形成・進化過程をたどってきたのかを明らかにすることを目指しています。
発表者:加藤 雄人(STAFF)
発表タイトル(英):Time scale and periodicity of the generation process of whistler-mode chorus emissions
イントロダクションの要約:
本発表では、VLF コーラス波動の発生メカニズム、その特徴的な時間スケール、および降下電子やオーロラ変動との対応を扱う。コーラスは上部・下部バンドやギャップなど複雑なスペクトル構造を示すが、その形成機構は統一的に説明されていない。他磁力線で発生した波動の伝搬・重畳により観測スペクトルを複雑化させている可能性も指摘されている。
コーラスの時間スケールには三段階の特徴がある。
第一に、数秒周期で強度が増減するスペクトル構造があり、複数のライジングトーンがまとまって現れる。
第二に、個々のライジングトーンの継続時間は約 100 ms で、場合によっては相互に重なりブロードバンド的に見える。
第三に、さらに短時間の「サブパケット」構造が存在し、電界強度が急増・急減を繰り返す。サブパケット内部で周波数が連続的に上昇しているのか、複数のサブパケットが連続して出現する結果なのかは未解明である。
これらの時間構造は降下電子やオーロラ変動と対応する。数秒周期のコーラス強度変化は、数 keV~数十 keV のロスコーン電子フラックスの変動と同期し、コーラスが降下電子を駆動していることを示唆する。約 100 ms のライジングトーン周期は、パルセーティングオーロラの 1~3 Hz の明滅周期と一致している。さらに、サブパケットに対応する数十ミリ秒以下の高速オーロラ変動も報告されている。
総じて、コーラスの発生タイミングや時間スケール――とくにサブパケット形成や数秒スケールの周期性――を決める物理過程は依然未解明であり、今後も重要な研究課題となっている。