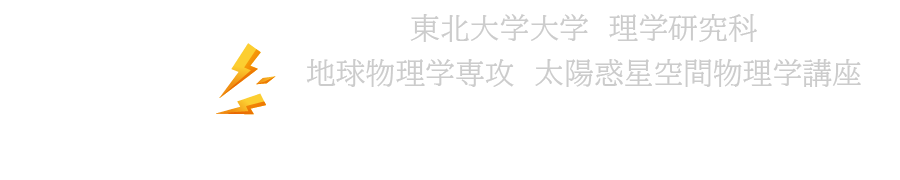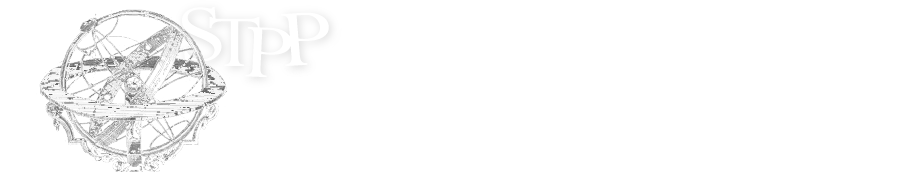宇宙地球惑星科学若手会夏の学校2025を開催しました
こんにちは、D1の神田です。
8月27日から29日にかけて、宇宙地球惑星科学若手会夏の学校2025を開催しました。
宇宙地球惑星科学若手会の運営はいくつかの大学で毎年持ち回りになっており、今年度は私たち東北大学が運営校でした。そして、若手会に参加している全国の大学生・大学院生が集う学生主導の研究会として、夏の学校が毎年開催されています。今年は若手会の運営校である東北大学が夏の学校を開催しました。
初日は東北大の一部メンバーが午前から会場入りし、他大学からの参加者を迎え入れる準備をしていました。会場は宮城県東松島市野蒜にある未来学舎KIBOCHAを利用させていただきました。

会場
午後からは全国の大学から集まった参加者が会場に到着しました。東北大メンバーを含め50人近くの学生にご参加いただきました。チェックインが終わると開校式と名大ISEEの岩井先生によるISEE大学院支援制度の紹介がありました。その後参加者のアイスブレークとPPARCの笠羽先生をお招きした招待講演が行われました。笠羽先生には「SGEPSS と惑星:これまでとこれから」と題して、日本の惑星探査の歴史と現在へのつながり、今の学生世代が担うであろう将来の惑星探査ミッションについてご講演いただきました。普段の学会や講演会ではなかなか聞けない、夏の学校ならではの話題が盛りだくさんの講演でした。

招待講演の様子
招待講演後は夕食・入浴ののちに懇親会・レクリエーションタイムがありました。宮城の地酒を取り揃えた懇親会や某番組風の「大学生格付チェック」により大盛り上がりでした。皆さんに楽しんでいただけたようで何よりです。
2日目は午前中が口頭発表、午後にはポスター発表を行いました。口頭発表は「磁気圏・学際科学」「大気圏、電離圏、太陽・宇宙天気」「惑星・衛星」の3グループに分かれて行い、全部で34件の発表がありました。最新の研究成果に関する発表や、夏の学校ならではのゆるっとした研究紹介・自己紹介的な発表も見られました。ポスター発表は全部で12件行われ、あちらこちらで活発な議論が行われていました。

口頭発表の様子
ポスター発表の後には体育館に移動してのレクリエーションが行われました。「気配切り」「紙飛行機飛ばし」「フリスビー飛ばし」の3競技を行いました。特に第2競技の紙飛行機飛ばしはさすがは普段研究に勤しむ学生という感じで、試作と飛行テスト、飛行機の形状と飛ばし方の理論(?)検討を重ねた大作が多く見られました。
レクリエーションの後にはBBQを行いました。山盛りのお肉をご用意いただき、食事と交流を楽しみながらのBBQとなりました。BBQ後には入浴ののち懇親会その2が行われ、2日目のプログラムは終了となりました。
3日目には朝食の後閉校式が行われました。閉校式では2026度若手会の運営校である京都大学から、時期夏の学校校長の発表がありました。その後今年度校長の神田から締めの挨拶をして、全プログラムが終了となりました。
昨年12月に前年度運営校からの引き継ぎを行って以来、8ヶ月にわたる準備を経て無事に夏の学校2025を終えることができました。今年度運営の総括や次年度運営校への引き継ぎなどまだ残っている作業はありますが、1番の目標である夏の学校が終了してひとまずほっと一息ついているところです。大変なことも多かったですが、50人規模の研究会を主催するという、とても貴重な経験を得ることができたのは良かったと思います。また、参加者としてもとても楽しい2泊3日になりました。
遠路はるばる全国からご参加いただいた学生・PDの皆様、ありがとうございました。また招待講演を引き受けてくださった笠羽先生と極地研の吹澤様(諸事情により当日は欠席)、大学院支援制度をご紹介いただいたISEEの岩井先生にもこの場を借りてお礼申し上げます。会場となったKIBOCHAの皆様にもお礼申し上げます。2泊3日大変お世話になりました。最後に、運営に参加してくれた東北大の皆さん、お疲れ様でした!

初日に撮影した集合写真。みなさんご参加ありがとうございました!
関連リンク
・夏の学校2025ホームページ
・宇宙地球惑星科学若手会